1月28日 日曜日
母が亡くなったと報せを受ける。こうなることは事前にある程度わかっていて、準備もしていたから、それほどの動揺はなかった。しかし、先週までかろうじてにせよ生きていたひとが、あっけなく死んでしまう、その動揺のなさ、「ひとが死ぬというのは命が移動することだ、そして移動するのは簡単なことだ」とでもいうような、ひとを食ったような単純さはなんなのだろう、と思う。
早朝に報せを受け、昼には飛行機に乗り、昼過ぎには死んだひとの顔をみて、夕方には葬儀の打ち合わせをしている。いろんなところから、死というものにひとが群がってくる。
人間とは移動する存在で、死とはたんにここからどこかへの移動だという思いを強くする。さっきまで座っていたところに脱ぎ捨てられた靴下のような。遺体。
1月29日 月曜日
葬儀屋からひとが来て、遺体になった母を装う。いわゆる「おくりびと」というやつだと思う。遺体を拭いたり、着替えさせたり、毛を剃ったり(とりわけ鼻毛を入念に)、化粧をしたりする。その間は鈴の音を鳴らしつづけるようにしてください、と言われ、祖母が鈴の音を絶やさないようにし、しばらくして兄が、そして私が、というように鈴を鳴らしつづける。こうすることになんの意味があるのだろう、江戸しぐさのようなものだろうか、と思ったりするが、死という慣れないもの(葬儀屋にさえ)、どうしていいのか誰もわからないものに対して、とりあえずこれさえしておけばよい、と安心させるためなんだろうと勝手に理解する。
遺体はとても冷たく、文字通り血が通っていない。横たえられた母の耳の、床に近い部分だけ血が溜まっているのか赤い。
母の遺体が入った棺を数人で持ち、もう母はひとではなくものになってしまったと、箱であれかばんであれ袋であれ、ひとがなにかにしまわれるとき、それはもうものなんだと、カルロス・ゴーンや、エスパー伊東のことを思う。
1月30日 火曜日
高見順『樹木派』。高見順にとって樹木とは、生と死のどちらをもあらわにするものなのだろう。木の若芽に生を見いだし、一方でつねに「枯れ」へと向かっているような死の相もそこにみる。ところどころにしみをつくり節くれだっている老人の手のような木肌もあるだろう。
母のひととおりの葬儀を終える。わたしが許すのでもなく許されるのでもない、それぞれの「許され」のような時空があった。おもに出棺のときに。遺影のhaunt感。なんといえばいいのだろう。
わたしたちはすでに「生き延びた者」であるのだから。生き延びsurviveしてしまった存在の書き継ぎ=記録としての日記=詩。母の死を記録しようとするわたしの生と、記録されたかぎりで死んでいるその日ばかりの出来事=暮らしと、死んでいないもの。その、それ。
2月8日 木曜日
久しぶりの週5日勤務に疲れている。帰って酒を飲んでゲームをして寝て、起きて出勤して職場のロッカーを開けて、ついさっきまでここにいたよな、と思う。仕事から帰ってきて家にいる時間がなかったかのように感じられる。スキップされる動画広告のように、「おうち時間」がスキップされる。
3月16日 土曜日
四十九日。ようやくというのか、あっという間にというのか、東京と帯広を頻繁に行き来する生活にひとまずの終わりを迎える。姿のない母親について考えることもほとんどなくなった。そのように思い出さなくなること、ある意味で汎化すること、自然化することが、日常のなかで弔うことの常態であり、たとえばこうした一文の語尾に気を配ることも喪の作業であるような気もする。
母の生前の友人であったというひともわざわざ出向いて、法要に出席してくれる。その後の食事の席での、祖母や叔母やそのご友人のぺちゃくちゃしゃべりのうちに、もうない母の話題が出たり消えたりしながら、知らない思い出が積もっていく。
死人に口無しだから、わたしは勝手に母と和解して、母の死をきっかけにして婚約したことも母に報告して、生前から良くも悪くも侵襲的だった母の視線や言葉をわたしの内に飲み込んで、みんなが寝るまで酒を飲んで寝る。
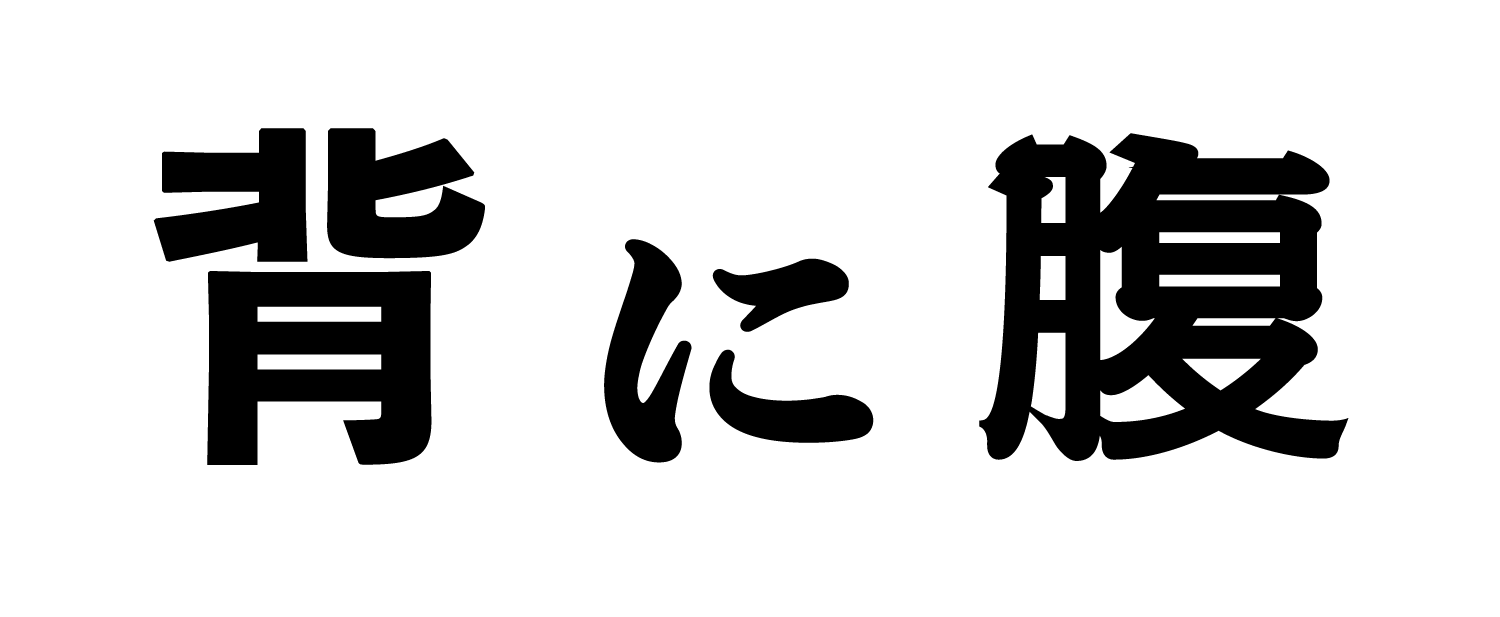

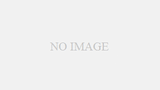
コメント