
『王国(あるいはその家について)』は、俳優たちのリハーサルの本読みを通して、俳優の声や身体が、どのように変化するのかを捉えた実験的作品である。
冒頭、ある出来事が提示され、警察の事情聴取のシーンから始まる。この時点で本読みやリハーサルは行われていない。そこから俳優たちはリハーサルを経て、あの日あの出来事のあと、手紙を書き、警察へ出頭するフィクションの場面で物語は終わる。
この手紙も脚本の高橋知由が作成し、リハーサルをへた俳優が、手紙の内容を精査し、感覚が身体に落ちていないものは編集された、と説明されている。当初は最初と最後のフィクションパートだけの小編を予定しており、本読みリハーサルに参加した俳優ふたりは本編には登場しないと説明されていたという。しかしのちにリハーサル部分をメインとした作品に修正された。
身体の変化を捉えるために様々な仕掛けを組み込み製作された本作は、まるでサウンドデザイナーがミキシングスタジオで様々な数値をチューニングするかのごとく設計されている。
想像力への変化は、役者のみならず観客にも働きかける。最後に設けられたという全体本読みでは、通常、ト書き(撮影場所や場所の様子、セリフにならない描写などが記される)は助監督などによって朗読されるところを、全員で黙読しながら進めるという形がとられた。
俳優たちが押し黙り、公民館のようなリハーサル室には空気音だけが響いている。このとき確かに観客は、観客をも、自ら物語を、能動的に、情景を生成する身体へ変化しつつあることを、多くの人が感じ取っていた。
この撮影時、監督である草野は俳優の声の変化に集中し、向き合っていたため、撮影のことは撮影に、音響のことは音響に全てを丸投げしている状態であったという。そのためカメラマンの渡辺寿岳は自身の感性を頼りにその場面を撮影した。彼もその時、物語を生成する能動的身体への変貌を遂げていたのではあるまいか。女性ふたりが会話するシーンで、そのシーンに登場しない男性の表情を収めていた。その時、とても奇妙で不思議な感覚になっていた。どのような表情かはわからないが、存在し得ない表情がそこに存在していたのだ。
しかしこの作品の驚くべきことは、リハーサルを積み重ねる段階で、徐々に情報を小出しにすることで「いかにして彼女は犯行に至ったか」を探るミステリー要素を付与している点にある。それらの要素は多くの観客を驚かせた。
しかしこの物語、果たして生活者であるわたしたちは、いかにして現実へ持ち帰るのか、その答えはまだ出ていないようにも思える。他の人はそうではないかもしれないが、わたしの映画に対する問いのひとつでもあるのかもしれない。つまり「俳優の身体が役を獲得する過程」は如何なるものか、如何に理解され、活用されうるものなのか、という「映画そのものを語る」行為とは少々離れた、生活のプラグマティズム的(実用的)な側面からわたしは考えていた。それは映画人の仕事というより、それを受け取った生活者の仕事でもあると考えている。
監督である草野なつかは撮影終了時は役を落としてもらうため振り返りのミーティングを行っていたという。であるにもかかわらず、俳優として参加していた澁谷麻美は演じる「亜紀」に引き寄せられ、撮影期間中スーパーの店員に高圧的な態度をとってしまったと対談で発言した。
この攻防は「憑依」ではなくコントロールされた身体性の獲得を意味するが、それはさておき、このことから、というか本作を通じてわかることは、本来フィクションは台詞や設定によって「役柄の輪郭」が与えられている。そこから俳優によって「台詞」から「輪郭」が、身体の中に落ちていき、身体それ自体から「台詞」が発せられるようになっていく。この映画はその変貌を捉えている(そうすると憑依というニュアンスもなんとなく理解できる、憑依とは自らの体験のみとのシンクロなのだろう)それを見せたのが本作であるし、すでに多くの人々に指摘されている点でもある。
しかしわたしはこの映画の、みなが指摘しているその部分を説明したいわけではない。わたしが本作を通して指摘したい点は「なぜ役者は役を演じているのか」わたしは論じたいことはその一点を貫いている。
「俳優が役の身体を獲得する過程」とは、あくまで生活において如何なる意味をもつか。
その糸口からでしか、この悲しい物語は生活へと還すことはできないのではないか、と思われた。いわば「俳優が役の身体を獲得する過程」とは実作者たち、プレイヤーたちのことばであって「俳優が役の身体を獲得する過程」とは生活において如何なるものか、それ自体にことばを与えなければいけないはずだ、と思ったのであった。
* * *
本作を観たとき、わたしは福居ショウジン監督作『ラヴァーズラバー』をふと思い出した。『ラヴァーズラバー』は90年代、インディーズムービー界でカルト的な存在感を放っていた福居ショウジンによる超大作で、カルト教団の全身をラヴァースーツに包み、シックスセンスを人工的に作り出し、超人化する人体実験に参加させられた男女の物語である。

被験者のひとりの女性はラヴァースーツに包まれた状態で、脳内に直接8mm映像を投射させられ、発狂と希望をみるという、あらすじを書いていてもおそろしく禍々しい物語なのであるが、それを爆音で上映するというなんとも奇怪な上映会で鑑賞したのであった。わたしはその映画を観た後、恐怖や嫌悪、悲しみなどのあらゆる感情もなく、涙を流していた。その時、
なぜ人は進んで、発狂しなければいけないのか。
ということを考えていた。なぜこれほどまでに、自ら恐怖を擬似的に体験しなければいけないのか、と。発狂を疑似的に体験することとは如何なることなのか、ということは、本作において、明らかに理解しがたい感情を、身体的に理解してしまうということにも当てはまったのだ。
* * *
わたしは今年、新型コロナに発症し、その後遺症から軽いパニックを伴う発作に悩まされた。その時の感情はまるで理解不能で、深夜に両親が自宅にくるせん妄を見て、両親を追いかけ深夜の道路に飛び出して、どこかに行ってしまう父を呼び止めるために叫んだり、突発的な自死欲求のようなものに襲われ、大丈夫、大丈夫、大丈夫とつぶやいていないと正気を保てなくなっていた。
それ以前と以後では、まるで世界が変わってしまったのだが、最も驚きだったのが、自分もこんなふうになるんだな、という子供みたいな感想であった。王国を観ている時、せん妄の日々に悩まされていた頃を思い出した。と同時にこの人はこのタイプのせん妄か、と妙に納得してしまった部分があった。
本作の意図とは全く違うのであろうが、彼女は「決定的なあの日」を何度も繰り返すわけではなく「4人でかわしたあの日常会話」を、自分の記憶の中で、時にディティールを変えて繰り返されていた、繰り返していた。まるで記憶ではあるまいか。
そして彼女自身ーこの彼女とは演じている澁谷麻美さんではなく作中の亜紀ーも「OKテイク」となる何かを探していたはずだ。決定的なあの出来事を、何度も、何度も、何度も、何度も繰り返している、と妙に納得してしまった。だからこそ彼女のあの台詞「(この永遠とも呼べるような)時間に裁かれている」にも妙に納得できてしまった。
発狂の擬似体験
で思いだすことは、落語家の立川談志、楽屋で身を悶えて言葉ではない何かを叫んでいる。取材者が聞くと、擬似狂態を演じているんです、自ら進んで狂態を演じることで本当に発狂することを防いでいるんです、と。
例えばこれを当事者の体験談としてひとに伝えることは困難であろう。そもそも当事者自身が言語化できなかったり、伝える意思を失ってしまう場合もある。そういった意味でこの作品が、この悲しい事件を取り扱ったことに、わたしなりに一定の決着をつけることができた。
さて「俳優が役の身体を獲得する過程」とは、あくまで生活において如何なる意味をもつか。という問いであるが。「俳優が役の身体を獲得する過程」ということばを一度かなぐり捨てないといけない。
まるで記憶ではあるまいか。
という言葉から解釈するのであれば、記憶と、その記憶がどのように再生されるか、の物語とも解釈できる。そう考えるとわたしは、この物語を極めて事件の事後的な記憶として見ているのだなと感じている。

長編映画デビュー作「螺旋銀河」が第11回SKIPシティDシネマ映画祭にてSKIPシティアワードと観客賞をダブル受賞した草野なつか監督の長編第2作。演出による俳優の身体の変化に着目し、脚本の読み合わせやリハーサルを通して俳優たちが役を獲得していく様子を、同場面の別パターンや別カットを繰り返す映像で表現。
2018年製作/150分/日本
配給:コギトワークス
劇場公開日:2023年12月9日
リアクション

Gbri田Ciou$太郎
エディタテストエディタテストエディタテストエディタテストエディタテスト

三上耕作
ふたつ目のコメントテスト
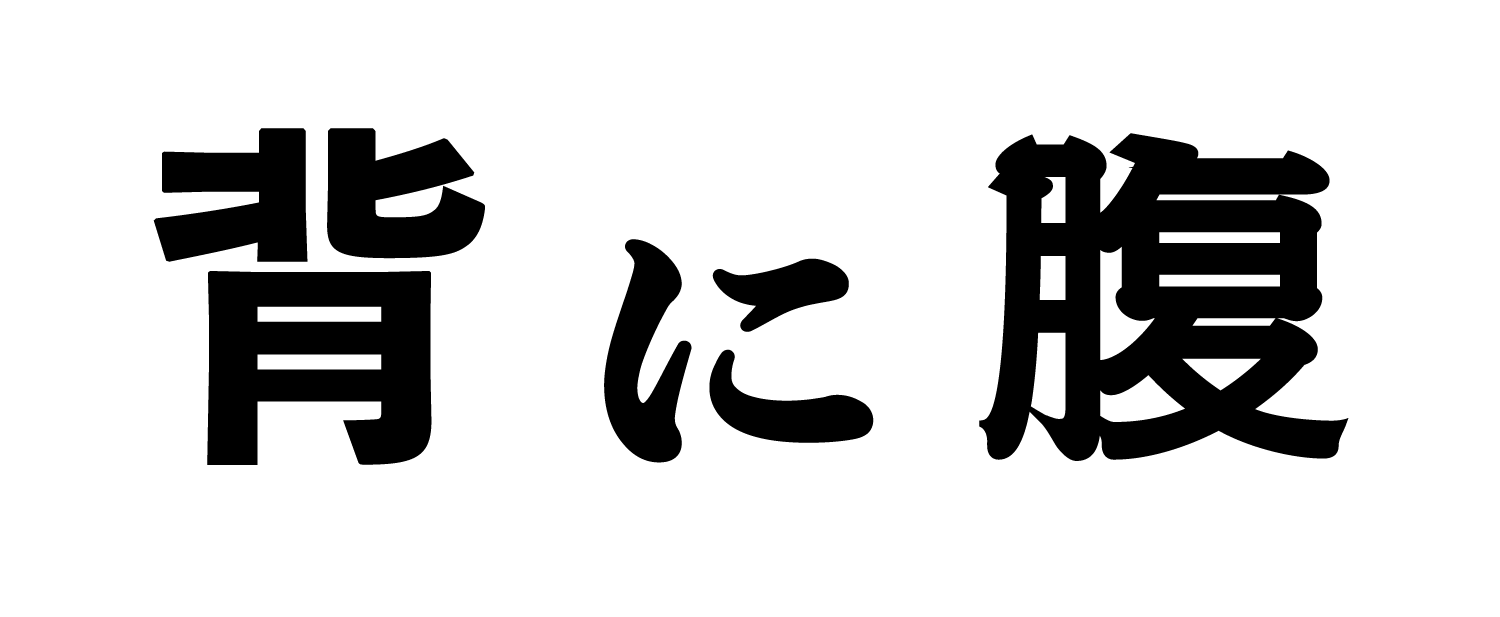

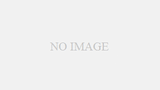
コメント